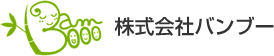「歳のせいか、耳が聞こえづらくなった」
「会話の中での反応が、だんだん少なくなってきている」
そんな高齢者の訴えや、高齢者の家族の会話を耳にしたことはありませんか?
難聴が認知症のきっかけになりえると言われています。今回は、認知症と難聴についての関連性とその対策について解説します。
【情報配信中】施設・ご自宅へのお薬のお届けや管理を薬局にお願いする方法など
認知症と難聴の関連性について
中年期に聴力低下がある人は認知症リスクが高いという報告があります。(1)
次に、認知症と難聴の関連性について詳しく説明します。
認知症とは
認知症は「認知機能が持続的に低下することで、日常生活や社会生活に支障がある状態」のことを指します。
例えば、記憶力や判断力、思考力の低下が認知症の症状とされています。気になる場合には早めに医師に相談しましょう。(2)
難聴によるコミュニケーションへの影響
「難聴になり、他人の話が聞き取れなくなる」「会話が成立しなくなった」等の経験からコミュニケーションが少なくなり、社会への関わりが減ることで認知機能に影響が出る可能性があります。難聴の進行とともに認知症のリスクも高まるという研究結果があり、認知症発症リスクが難聴のない場合と比べて、中等度難聴郡が3倍、高度難聴郡が4.94倍になると報告されています。(3)
老人性難聴の3つの特徴
難聴が認知機能に影響を及ぼすことを知ってもらいました。具体的な難聴の特徴について解説します。(4)
1.高い音が聞こえなくなる
電話の呼出音や体温計の音などの高周波数の音が聞こえなくなります。昨今はコロナウイルスの関連で自宅で検温することも多いと思います。ご家族の方の検温時には注意してみましょう。
2.小さな音が聞こえなくなる、&大きすぎても聞き取れなくなる
高齢者の方に大きな声で話しかけた経験はあるのではないでしょうか?小さい音が聞こえづらくなることはご存知の方が多いでしょう。ただ、聴覚の機能が全体的に低下しているため大きすぎても逆に聞き取れないということもあります。声の大きさは相手との会話の様子によって変えてみる方が良いでしょう。
3.早口で話された言葉が理解できなくなる(時間分解能の低下)
高齢者同士の会話のペースはゆっくりであると感じたことはありませんか?加齢とともに早口で話された言葉が聞き取れなくなります。ゆっくりした会話を意識して、コミュニケーションが良好になる工夫ができるといいですね。
聞こえのチェックシート
こちらは聞こえにくいと感じている方が、どのくらい日常生活に影響があるのか、というチェックシートです。
以下の10個の質問に、「はい」「ときどき」「いいえ」で答える形式になります。
聞こえのチェックシート
| E1 | 初対面の人と会うとき、聞こえないことで気まずい思いをしたことがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| E2 | 家族と話をするとき、聞こえないことでストレスを感じますか? | はい | ときどき | いいえ |
| S3 | 小声で話しかけられると、聞き取りにくいことがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| E4 | 聞こえないことで、不利益があると感じることがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| S5 | 友人や親類、近所の人と話をするとき、聞き取れなくて困ることがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| S6 | よく聞こえないために、集会や会合への出席をためらうことがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| E7 | 聞こえのことで、家族と口論になることがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| S8 | ラジオやテレビの音が聞き取りにくいことがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
| E9 | 聞こえないことで、やりたいことが十分にできないと感じますか? | はい | ときどき | いいえ |
| S10 | レストランなどで、話し声が聞き取れないと感じることがありますか? | はい | ときどき | いいえ |
出典:難聴障害度質問票(短縮版)HHIE-S
「はい」は4点、「ときどき」は2点、「いいえ」は0点です。合計が10点以上で軽・中等度の難聴、24点以上で重度の難聴の可能性がありますので、聴力測定を受けることをおすすめします。
補聴器を活用しよう

難聴に対する対策の1つとして「補聴器」の活用があります。補聴器の活用により、コミュニケーションが円滑になります。また、うつ傾向の抑制や認知機能に対しても有益であると言われています。(4)補聴器購入にあたっては補助制度もあります。各市町村に問い合わせてみて導入を検討してみるのはいかかでしょうか。(5)
まとめ
今回の記事では老人性難聴と認知症の関連性について解説しました。難聴に気づき、対策をすることで認知症の発症予防にもなります。ご家族の会話から早期発見に繋がることもあるので、コミニュケーションをとるなかで意識してみるのもいいかもしれませんね。
【参照】
(1)Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission
(3)Hearing loss and incident dementia
(5)補装具費支給制度の概要