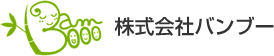介護現場で、不眠症の薬を飲まれている高齢者の方を見かけますよね。
筆者も、在宅業務を行っていた頃、不眠症の薬を飲まれている方と多く接してきました。
不眠症の薬はさまざまな種類があり、また注意が必要です。
今回は、不眠症で使われる薬、管理する上での注意点を解説します。
【情報配信中】施設・ご自宅へのお薬のお届けや管理を薬局にお願いする方法など
不眠症とは
不眠症とは、寝れない状態が1ヶ月以上続き、さまざまな体調不良(体の怠さ、集中力の低下、食欲の低下など)が起こることです。
不眠症は、寝付きが悪い(入眠障害)、夜中に目が覚めてしまう(中途覚醒)、朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)、寝た感じがしない(熟眠障害)の4種類あります。
不眠症で使われる薬について
不眠症で使われる薬は、不眠症の種類によって使われる薬が違います。(1)
- 寝付きが悪い(入眠障害)
薬の効きが早く、効果の持続時間が短い薬を使用します。(超短時間作用型・短時間作用型)
商品名:ハルシオン、レンドルミン、ロラメット、リスミー、マイスリー、アモバン、デパス、ロゼレムなど
- 夜中に目が覚めてしまう(中途覚醒)
薬の効きが比較的に早く、効果の持続時間はある程度続く薬を使用します。(短時間作用型・中時間作用型)。
商品名:レンドルミン、デパス、リスミー、ロラメット、サイレース、ベンザリン、ユーロジンなど
- 朝早く目が覚めてしまう(早朝覚醒)
薬の効き目が長く続く薬を使用します。(中時間作用型・長時間作用型)
商品名:サイレース、ベンザリン、ユーロジン、ソメリン、ドラールなど
- 寝た感じがしない(熟眠障害)
薬の効き目が長く続く薬を使用します。(中時間作用型・長時間作用型)
商品名:サイレース、ベンザリン、ユーロジン、ソメリン、ドラールなど
※上記に紹介した以外の薬も使われる場合があります。
不眠症の薬は、不眠症の種類によって使い分けることが大事です。
また薬の効き目は個人差があるため、あくまでも目安の使い方になります。

薬を管理する上での注意点
ここでは、不眠症の薬を管理する上でのさまざまな注意点を紹介します。
- 決められている量を守る
薬は、安全に飲むことができる量がそれぞれ決まっています。また高齢者は、薬の効果や副作用が強く出てしまうことがあります。そのため、薬の種類によっては、安全に飲むことができる量を少なめに設定しているものもあります。安全に薬を飲むために、決められた量を守るようにしましょう。
- 薬の種類によって出してもらえる日数に制限がある
不眠症の薬は、1回に出してもらえる日数に制限があるものが多く存在しています。もっと多めの日数を出して欲しいと思うこともあるかもしれません。基本的に制限を超えた日数の量を出すことができないので、「もっと出して下さい」と無理なお願いはしないようにしましょう。
- 転倒する危険性があるため、寝る直前に飲むようにする
高齢者の転倒の原因の1つに「薬による転倒」があります。(2)
転倒の可能性がある薬は、血圧を下げる薬、気持ちを落ち着かせる薬、アレルギーの薬などさまざまあります。今回ご紹介した不眠症に使う薬も転倒の可能性がある薬です。転倒の危険性を回避するため、寝る直前に飲むようにしましょう。ベッドやお布団の上で飲んで、そのまま寝るのが1番安全ですね。
- ご本人の判断で薬をやめさせない
ある程度の期間飲んでいると「薬がなくても大丈夫」「薬をやめたい」と思う方もいるかもしれません。ご本人の判断で薬を飲むのをやめてしまうと、症状が悪化してしまう場合があります。不眠症の薬は、症状を見ながら少しずつ薬の量を減らしていきます。薬をやめたり、量を少なくしたいと思った時は、必ず担当の先生に相談するようにしましょう。(3)
- ご本人の手の届かないところで管理する
薬の効果を感じない場合、「効果がないから追加でもう1錠飲もう」と勝手な判断で薬を飲んでしまうことがあります。また、薬が手元にないと落ち着かない(依存症状)と感じてしまう場合があります。そうならないためにも、薬は手の届かない場所で管理し、ご本人からの要望がある場合は必要分だけ渡すようにしましょう。
- 薬は水で飲むようにする
水以外の飲料水で薬を飲むと、薬の効果に影響を与えてしまうものがあります。薬を飲む時は、水で飲むようにしましょう。
- 他に飲んでいる薬がある場合、主治医や薬剤師に伝える
高齢者は、高血圧・糖尿病・パーキンソン病などさまざまな持病を抱えている方は普段からたくさんの薬を飲まれている方も多いですよね。
不眠症の薬は、薬の種類によって飲み合わせが良くないものがあります。必ず主治医や薬剤師に、他に飲んでいる薬を伝えるようにしましょう。

ご家族の方が薬の管理をサポートしましょう。
今回の記事では、以下について解説しました。
・不眠症とは、寝れない状態が1ヶ月以上続き、さまざまな体調不良が起こること。
・不眠症の薬は、不眠症の症状によって使い方がある。
・不眠症の薬の管理には注意点がある。
筆者が薬剤師として勤務していた時、「薬の効果を感じないから、勝手に追加で服用した」「薬を飲みたくないから勝手にやめた」とおっしゃっていた方がいました。また、自分の判断で薬を増やしたり、やめてしまったりした結果、体調に影響が出た方もいました。
不眠症の薬の種類によっては、効果の強い薬もあります。ご本人の判断で飲み方を変えないように管理のサポートをしましょう。薬に効果を感じなかったり、薬をやめたいと感じたりした場合は、担当の先生に必ず相談するようにしましょう。
【参照】
(1)第1版 薬がみえるVol.1(p262-265)
(2)転倒の疫学